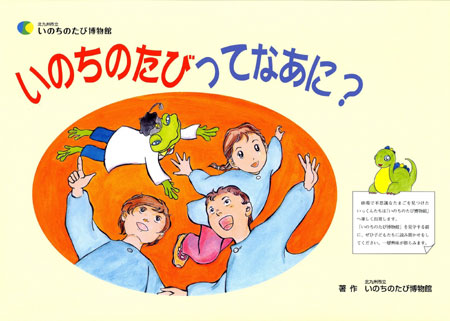堀切辰一コレクション時代布目録「襤褸」
庶民生活史研究家堀切辰一氏は、庶民が用いた衣類・布類を収集し、その生活実態を探求するという独自の研究分野を開拓しました。堀切氏は収集資料のうち、3,500点を博物館へ提供するとともに、各資料に詳しい解説を付す作業を長年続けました。堀切氏のコレクションは「襤褸」と名付けられており、当館を代表するコレクションの一つです。
目録では3,500点の資料を晴着・外出着・普段着・仕事着・特殊着・中着・下着・制服・補助衣・帯類・家財衣・諸布類の12項目に分類し、写真と堀切氏による解説を収録しました。3回に分けて発行した堀切コレクション時代布目録『襤褸』」は、第1分刷から第3分刷を揃えて1冊のものになります。その続編として、晴着・外出着を収録した「続編第1巻」、普段着・仕事着・特殊着・中着・下着を収録した「続編第2巻」、制服・補助衣・帯類・家財衣・諸布類を収録した「続編第3巻」があります。
門司文書
門司文書は中世の北九州市域に勢力を保持していた門司氏の子孫に伝えられていた古文書です。平成15年(2003)3月、ご子孫門司尚子様から北九州市に対し寄贈されました。交通の要所である北九州では、時代の変わり目にはたびたび戦乱にまきこまれ、古い時代を語る資料があまり多く残っていません。中世の動乱期の北九州の歴史をよく伝え、また、様々な勢力とかかわりながら勢力を保持した門司氏の活動が窺えるなど、数量・質ともにすぐれた貴重な文化財であることから、平成18年(2006)に福岡県指定文化財となりました。
門司氏は、鎌倉時代の寛元2年(1244)にその祖下総親房が関東より門司に下向し、一族は門司六ヶ郷に土着していきました。六ヶ郷にちなみ門司氏も片野系・大積系・吉志系・楠原系・柳系・伊川系に分立しています。西の麻生氏、東の門司氏と並び称される有力武家で、門司文書には後醍醐天皇や足利尊氏、大内義隆、毛利元就・輝元などからの文書も含まれ、総数は60点を数えます。内容的にも、南北朝時代には関門海峡を渡る敵方の船を兵船で襲うことなど、地域の歴史の特徴をよく伝えるものとなっています。その他、系図2巻があり、うち1巻は永正7年(1510)に書かれたもので、その貴重さは計り知れません。
小森承之助日記
小倉藩の大庄屋を務めた小森承之助(諱は盛郁、1825~75)が、大庄屋に就任した安政5年(1858)8月末から明治4年(1871)までの約13年間にわたって記した日記です。ただし、慶応2年(1866)6月から同3年の期間のものは確認できていません。
大庄屋とそれを補佐する子供役は、在勤中は本姓を名乗らず、手永名を名乗ることになっていました。承之助の本姓は「友石」ですが、小森手永の大庄屋を務めたため「小森承之助」を通称にしており、そのため小森承之助日記と呼ばれます。
日記には、承之助が大庄屋在任中の役向きの諸事が詳細に書かれています。小倉藩政の機構や、その運用の状態が分かり、また同藩の政治・経済動向、それに対応する庶民の生活全般―農耕、貢租、商業、宗教、習俗など―についてもうかがい知ることができる貴重なものです。加えて、この日記が書かれた時期は幕末期で、幕末維新の厳しく流動する世情を反映しており、同時期の小倉藩を調査・研究する上で不可欠な文書です。
昭和43年(1968)日記20冊が福岡県有形民俗文化財に指定され、平成7年(1995)から同11年にかけて全5巻で翻刻・刊行しました。
中村平左衛門日記
小倉藩の大庄屋を務めた中村平左衛門(諱は維良など、1793~1867)が、文化8年(1811)から慶応2年(1866)までの約56年間の日記のうち、一部欠落があるものの現存するものを全て翻刻したものです。昭和57年から平成5年までに、現存する37冊を全10巻に分けて刊行しました。
日記には、毎日の出来事が綿密に記されており、当時の政治・治安・租税・凶荒救恤・習俗・行楽・宗教・交通・産業・土木・金融などのあらゆる面について知ることができます。さらに江戸時代後期から幕末期の小倉藩の政治動向と、それに対応する人々の様相が具体的に把握できる貴重な史料です。
昭和38年(1963)日記35冊が福岡県有形民俗文化財に指定され、さらに平成14年(2002)新たに発見された2冊が追加指定されました。
![北九州市立自然史・歴史博物館[いのちのたび博物館]](/assets/img/common/logo.svg)