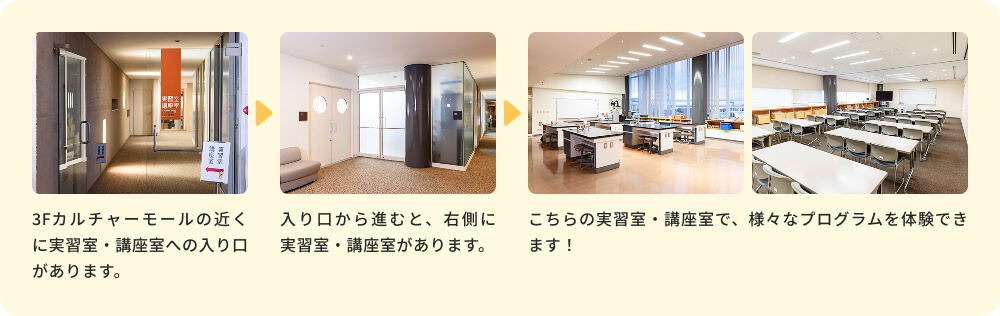展示見学だけでなく、博物館で「体験」していただくための「体験学習プログラム」をご用意しております。 事前申込と別途料金が必要ですので、ご希望の場合は、あらかじめ博物館へご連絡下さい。
石膏を使ってアンモナイト等の化石レプリカを作ります。固まったレプリカを型から取りだす作業には、誰もがワクワクすることでしょう。 実際に本物の化石を見ながら作業を行うことで、観察力を養うことができます。

ペットボトルとビーズ玉を使って顕微鏡を作ります。 身近なものを利用して、手軽に顕微鏡を作ることができるという新鮮な驚きと喜びを感じることができ、探究心や自然愛護の気持ちを育むことができるプログラムです。 ペットボトルホルダーがつきます。

弥生時代から古墳時代にかけて身分の高い人たちが身に着けていた勾玉づくりに挑戦するプログラムです。滑石(かっせき)を紙やすりで削り、形を整えたら、皮ひもを通して完成です。 世界にひとつしかない自分だけの勾玉が出来た時、古代のロマンにひたれる気がします。

古代中国に起源を持ち、日本では弥生時代の遺跡などから出土する青銅製の鏡です。プログラムでは石膏を使いミニモデルを作ります。美しく仕上がった鏡に、古代の人たちの思いを感じることができるかもしれません。

栃木県那須塩原市にある化石園の岩石を素材とし、化石の発掘体験を行います。塩原は、保存の良い化石が豊富に産する日本の代表的な化石の産地です。小学校の児童でもハンマーを使って化石を取り出すことができます。植物の化石が多く産出しますが、魚や昆虫類の化石も発見されています。自分で発掘した化石は標本にして持って帰ることができます。

古代のお金で最も知られる「和同開珎」(飛鳥時代)をその時代の作り方で再現する楽しいプログラムです。作成キットを使い、溶かした合金を鋳型に入れ、短時間で枝銭を作ります。銭貨の歴史を学ぶことで、日本の貨幣経済がどのように進んでいったのかを考えるきっかけとなる体験学習です。

小学校6年生の理科「土地のつくりと変化」は観察・実験をするのがなかなか難しい単元ですが、当館の実験器具や資料を使って、博物館ならではの実感を伴った学習を展開することができます。
実際の地層から採取した「はぎとり地層」を使って、地層の様子を観察します。
川の模型(ジオラマ)を使って、流れる水のはたらきで「浸食」「運搬」され、海底に「堆積」される様子を実験し観察します。
実物の岩石や複数の化石資料を観察するなど、博物館ならではの資料を触りながら観察します。

小学校3年生の社会科単元「わたしたちの市の歩み」のうち「かわる道具とくらし」の学習支援とした体験プログラムです。
おじいちゃん、おばあちゃんより前の時代の家として、明治時代の民家を見学するコーナーです。歴史課学芸員による解説を聞きながら学びます。(状況により、昭和30年代の社宅の見学に変更する場合があります。)
昔の道具(ひのし、がんどう、箱膳、黒電話)を実際に手に取り触ってみながら道具の使い方を調べることを通して先人の知恵を学んでいきます。
石臼を使って大豆をきな粉にする体験です。実際に石臼をひくことで、道具の使い方だけでなく、当時の人の苦労や知恵、工夫なども学ぶことができます。